トカゲと聞くと、陸上でじっとしているイメージを持つかもしれませんが、実は呼吸の仕方にも多様な進化が見られます。
この記事では、トカゲの呼吸器官の基本構造から、珍しい水中での呼吸方法まで、驚きに満ちた呼吸の仕組みを紹介します。
カエルやイモリとの違いも含めて、トカゲの呼吸にまつわる秘密を一緒に探っていきましょう。
この記事で分かること:
- トカゲの基本的な呼吸器官と構造
- トカゲと両生類(カエルやイモリ)との呼吸の違い
- トカゲの呼吸が荒くなる理由
- アノールトカゲの水中呼吸の仕組み
- 一方通行の肺の構造とその意味
トカゲは肺呼吸をする爬虫類
トカゲは、誕生した時から死ぬまで完全な肺呼吸で生きる動物です。私たち人間や鳥と同じように、肺を使って空気中の酸素を取り入れ、二酸化炭素を排出します。
両生類のようにエラ呼吸や皮膚呼吸を併用することはなく、トカゲの肺は非常に発達しています。
そのため、水のない乾燥した環境でも生存できるという強みがあります。
呼吸器官の構造と特徴
トカゲの呼吸器官は、気管から肺へと空気を通すシンプルな構造をしていますが、一部の種では「一方通行」の気流システムが確認されています。
一方通行の呼吸システムとは?
米ユタ大学の研究では、サバンナオオトカゲの肺の中で、空気が一定方向に流れる「一方通行型」の呼吸が発見されました。
これは高山を飛ぶ鳥と似た構造で、酸素をより効率よく取り込むことができます。
この仕組みは、約2億年前の大量絶滅を乗り越えた進化の産物だとも言われています。
トカゲの呼吸が荒くなる理由
トカゲは変温動物であり、外気温に体温が左右されるため、気温の上昇やストレス、興奮時に呼吸が早くなることがあります。
特に捕食者から逃げた直後や、繁殖期に興奮したオスなどは、胸を大きく膨らませて速い呼吸を行うことがあります。
これは異常ではなく、生理的な反応です。
アノールトカゲの水中呼吸

ごく一部のトカゲ、特に中南米のアノールトカゲの仲間は、水中でも「呼吸泡(rebreathing bubble)」を使って15〜20分もの潜水を可能にしています。
泡を使った「再呼吸」の仕組み
アノールトカゲは、鼻先に吐き出した空気を泡として保持し、その中の酸素を繰り返し吸い込むことで水中で呼吸します。
これはまさに天然のスキューバ装置のようなもので、泡は撥水性の皮膚によって支えられています。
さらに、泡は不要な二酸化炭素を水中に排出する働きも持っているとされており、まさに「生きたエアフィルター」と言えるでしょう。
イモリやカエルとの違い
| 特徴 | トカゲ | イモリ・カエル |
|---|---|---|
| 主な呼吸法 | 肺呼吸のみ | エラ→肺+皮膚 |
| 幼生の呼吸 | 肺 | エラ |
| 皮膚呼吸 | ほぼしない | 活発に行う |
| 水中行動 | 種による | 多くが適応 |
トカゲは肺呼吸が前提であるため、カエルのようにぬれた肌から酸素を吸収することはできません。
その代わり、肺の効率を高める方向で進化してきました。
まとめ:呼吸も多様な進化の証
- トカゲは基本的に肺呼吸のみを行う爬虫類である
- 一部のトカゲは鳥のように一方通行の肺を持つ
- アノールトカゲは泡を使って水中でも呼吸できる
- 呼吸の速さは環境や体調により変化する
- 両生類との大きな違いは呼吸法にある
一見単純に見えるトカゲの呼吸も、環境への適応と進化の結果、非常に洗練された仕組みを持っています。
次にトカゲを見かけたときは、その小さな体の中で行われている呼吸のメカニズムにも思いを馳せてみてください。


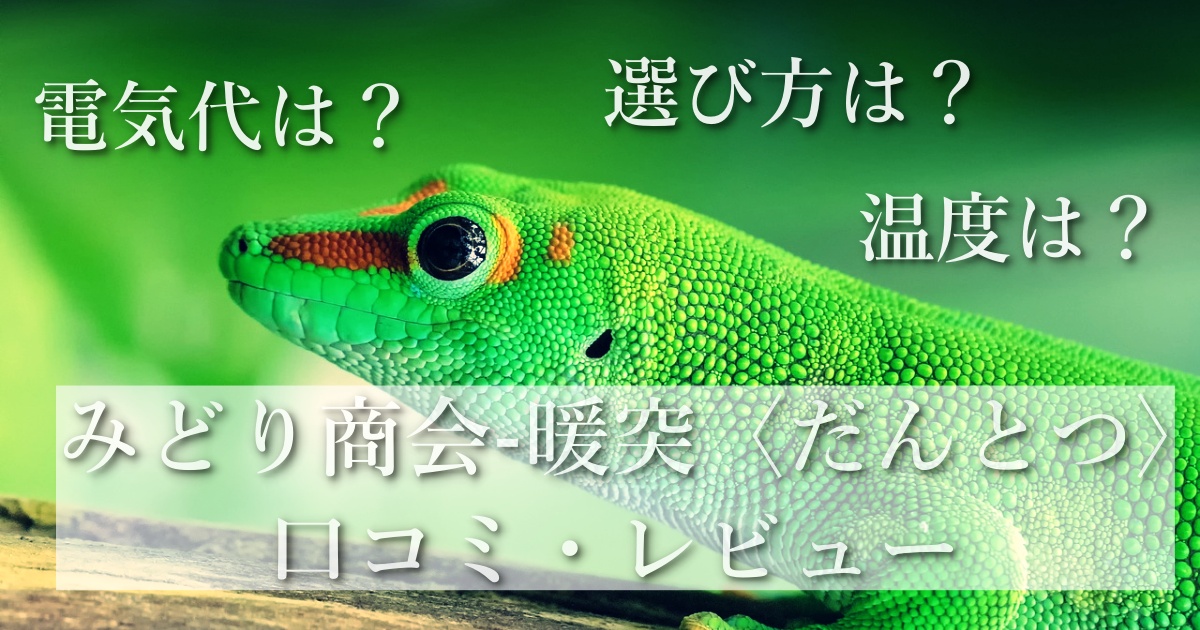



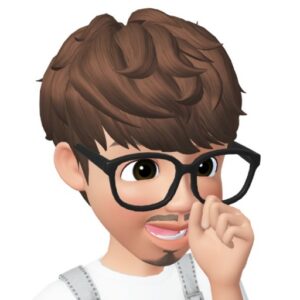
参考になった方は、ぜひコメントを!