身近な存在でありながら、実は驚くべき能力と進化の歴史を持っている「トカゲ」。
この記事では、トカゲの体の中の構造や表面の特徴、尻尾が切れる仕組み、世界中の生息地や進化の過程まで詳しく紹介します。
意外と知らないトカゲの秘密に迫っていきましょう。
この記事で分かること:
- トカゲの体の中の構造と特徴
- 体表の様子や色の変化について
- 尻尾が切れる驚きの仕組み
- 世界中の生息地と生活場所
- トカゲの進化の歴史と変化
トカゲの体の基本構造
トカゲは爬虫類の一種で、有鱗目(ゆうりんもく)というグループに属しています。
4本の足と長い尾を持ち、全身がうろこで覆われているのが特徴です。
地上や木の上、水辺など、さまざまな場所に適応して生活しています。
トカゲの体の中
トカゲの内臓や骨格は、哺乳類とは異なる構造を持っています。
消化器官は食性によって多少異なりますが、昆虫食や植物食など、多様な食性に対応しています。
呼吸は肺で行い、心臓は3つの部屋(2心房1心室)を持つ構造です。
まぶた・舌・耳のしくみ
トカゲの多くは、上下にまぶたを閉じて目を守ることができます。
一部のトカゲには透明な下まぶたがあり、目を閉じたままでも周囲を見ることができます。
舌は長く、先が二股に分かれていて、空気中の匂い物質をキャッチしてヤコブソン器官で嗅ぎ取ります。
耳は外から見える耳孔があり、鼓膜で音を感知します。
トカゲの体の表面の様子と変化

トカゲの表皮は「ケラチン」というタンパク質からできており、水分の蒸発を防ぐ役割を果たします。
これは人間の爪や髪の毛と同じ素材です。
一部のトカゲ、特にカメレオンなどは、環境や気分、体温に応じて体の色を変えることができます。
これには細胞内の色素胞が関与しており、光の反射や屈折を変えることで色が変わります。
尻尾が切れる仕組み「自切」
トカゲといえば「尻尾切り」。
これは「自切(じせつ)」と呼ばれる現象で、尻尾の骨にある“脱離節”という切れ目が刺激によって働き、尾が自然に外れる仕組みです。
筋肉の収縮により出血はほとんどなく、しばらくピクピクと動くことで外敵の注意をそらし、逃げる時間を稼ぎます。
切れた尻尾は数ヶ月かけて再生しますが、元通りにはならず、やや太く短い形で生えます。
また、再生尾は骨ではなく軟骨組織になります。
トカゲの生息地と生活場所
トカゲは世界中に約4,500種類以上確認されており、温帯・熱帯の森林から砂漠、高山地帯までさまざまな環境に適応しています。
日本でもニホントカゲやニホンカナヘビなどが見られます。
- 樹上:カメレオン、エリマキトカゲなど
- 地上:ニホントカゲ、アガマ類など
- 水辺:フィリピンホカケトカゲ、カイマントカゲなど
日中に活動する昼行性の種が多く、周囲の気温に応じて体温を調整しながら生活します。
トカゲの進化の歴史と分類
トカゲは約3億年前に出現したとされる爬虫類の中でも、有鱗目に属する動物です。
トカゲとヘビは共通の祖先を持ち、進化の過程で足を失ったのがヘビだと考えられています。
卵生から胎生へ進化中の種も
オーストラリアに生息するスキンク科の一部では、卵生と胎生を併せ持つ珍しい繁殖形態が確認されています。
寒冷地では、卵を体内で孵化させてから出産する「卵胎生」が有利とされ、進化の途中段階とみなされています。
まとめ:トカゲは驚きに満ちた生き物
- 骨格・内臓・皮膚などが独自に進化している
- 色の変化や尻尾切りといった特殊な能力を持つ
- 地球上の多様な環境に適応し世界中に分布
- 進化の途中にある繁殖方法を持つ種も存在
このように、トカゲの体はまさに進化と適応の宝庫です。
身近な存在でも、奥深い魅力がたくさん詰まっています。


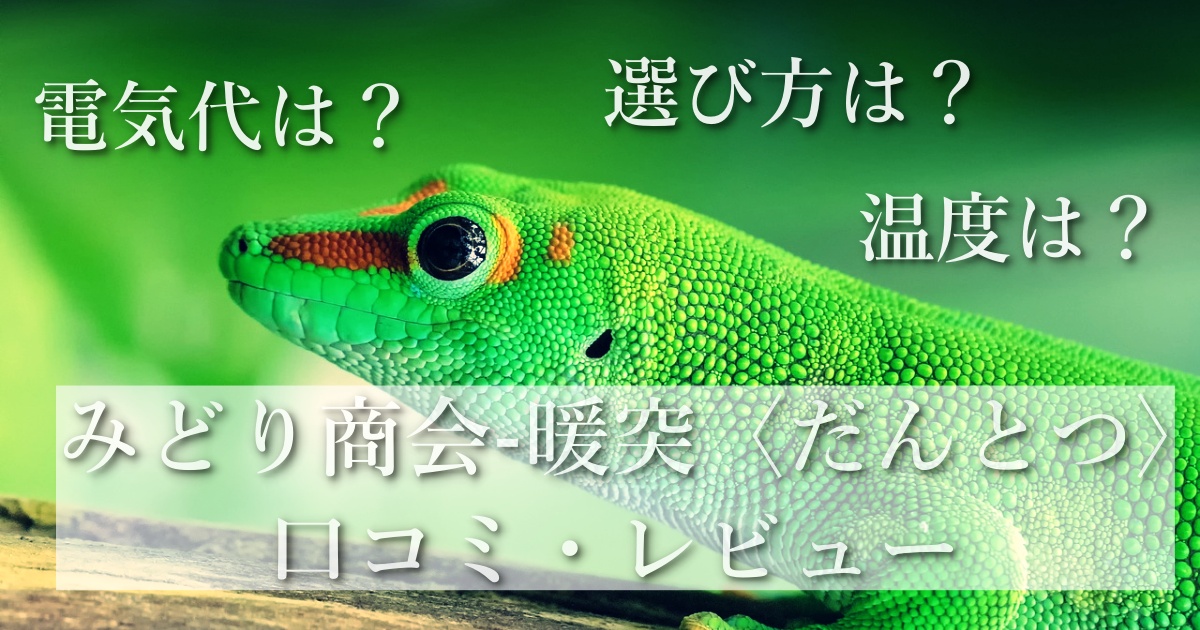



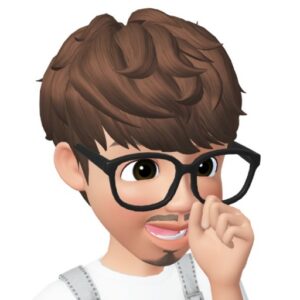
参考になった方は、ぜひコメントを!